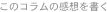第38回:アダルトなスクール
更新日2002/11/28
「パーッ!」
仕事を終えてダウンタウンを歩いていると、綺麗なアウディのセダンがクラクションを鳴らして私の横に止まった。助手席のウインドウガラスが開き、
「アニキ! 今から学校でしょ。乗って行きません?」
台湾から来た遊学生のウーが、車の中から大声で叫んだ。3歳年下の彼は台湾で兵役が終わったのでシスコに遊学に来ていた。「兄貴」程度の日本語が話せるが、アメリカにきてまだ半年なので、私と英語力はさほど変わらなかった。
彼とは、アダルト・スクールと呼ばれる語学学校で知り合ったのだ。ウーはアジア人としては大柄で、日本人に似ているが、台湾華僑の金持ちの息子らしく、郊外の高級アパートに住み、高級車を乗り回している。しかし、学校でも私にいつも付いて廻るのは一度学校の帰りにベトナム料理屋でラーメンをご馳走したためか、我々のクラスには、私たちのほかには、大陸系の中国人かメキシコ人しかいなかったためであろう。
アダルト・スクールは、ダウンタウンにある移民のために開設された無料の学校で、レベルに合わせて誰でも入校できる。フルタイムで昼間に仕事をしている私は、夕方からのクラスを取って英語の授業を受けていた。講師は、ボランティアの大学生や一般の米国人である。夜のクラスに参加する生徒の殆どは、米国に移民したての定職を持った人たちで、18歳~50歳くらいと年齢層は幅広い。
日本と異なることは、一応はテキストに沿って授業が進められるが、すべてが英語で行われることと、やたらとカンバセーション(会話)が多く、容赦なく人前に出て喋らされることである。私たちの英語は、まだ日本の中学生レベルであるが、それでも日常の会話も充分できる。
台湾人のウーは、大陸系の中国人がよほど嫌いなようで、
「授業中は、中国語を喋るなっ!」
と、話し合いで煮詰まってしまった中国人たちに対して英語で叫ぶ。どうしても、同人種が集まれば、祖国の言葉を喋ってしまう気持ちは、よく分かるのだが…。
夕方6時からの授業は、夜10時に終わる。ウーといつものベトナム料理屋で遅い夜食を食べていると、
「ジュリーサは、どうも兄貴のことに気があるらしいですぜ。」
と何処でそんな情報を入手したのか、とんでもないことを言い始めた。
「じゃ今度、デートにでも誘うかッ。」
と冗談で言うと、真面目な顔で、
「じゃ、今度話を付けときます。」
と何気なくその時の会話は終わった。
彼は情報屋で、クラスの誰が何処で働いているとか、身辺の状況についてやたらによく知っているのだ。
次の金曜日の夜、学校が終わると同じクラスメイトであるメキシコ人のジュリーサが、一人で私の方に近付いてきた。
「貴方、ダンスが得意なんだって! 今晩、サルサ踊りに行かない?」
と舌足らずの英語で私を誘ってきた。彼女は、スペイン系の血が多いのか、白人に近い顔立ちで、いつも派手でタイトなジーンズをはいたグラマーな20歳の女の子だった。ラテン系の女性は、こういう時には意外に積極的である。
しかし、腹の中ではウーの奴、適当なことを言いやがって、何時私がダンスの話などしたんだ? と憤慨したが、ジュリーサの笑顔を見れば悲しいかな、
「ああ、そうだね、たまには…。」
と答えてしまった。ウーを見れば、彼女の後ろで、私に親指を立てていた。
学校が終わったその足で彼女の行きつけの店に二人で入り、軽くタコスを食べ、ポルチャ-タ(ジンジャ-入りドリンク)を飲んだ。シスコのミッション通りと呼ばれる街道の16番から24番までの約5Kmは、活気のあるメキシコ人街でスペイン統治時代の古い教会も数多い。
食事中、ジュリーサに、
「いつもは、ディスコで踊っているの?」
と質問されたが、
「そうだね、でも最近は行ってないけど…。」
と答えた。本当のところ、日本でディスコはおろか盆踊りくらいしか踊ったことはないのに…。不安で帰りたくなる気持ちを抑えながら、今回のデート会場であるサルサ・ダンスのホールへ向かった。
ホールは市内のメキシコ人地区にある体育館だった。中に入るとディスコのようなボックスシートや、休憩して酒を飲むカウンターもない。つまり踊りに徹する訳である。基本的に、壇上のステージで熱唱するボーカルとライブミュージックに合わせて、参加者は男女ペアで踊る訳だ。踊りを見ていると、以外に曲のテンポは早くはないが、足のステップは非常に早く、ペアで踊るのは困難を極めそうなことは、必至だった。
「踊りましょう!」
とジュリーサは、積極的に私の手を引くが、なかなかホールの中に踏み出せなかった。やっとの思いで勇気を振り絞って中に入ったが、お互いで両手をつなげば彼女の足を踏まないようにするのが精一杯だった。
彼女は深いVネックのシャツを着ていたので、密着していると目のやり場にも困った。ジュリーサは、サルサ・ダンスが上手でリードされっぱなしであった。
ボーカルがスローなバラードを熱唱し始めると、チーク・タイムがやってきた。
「貴方、本当は、ダンスが苦手なのね。」
と彼女は耳元で囁いた。
「ごめん。」
私は素直にあやまった。
「ウーは、いい友人ね。」
と彼女は一言言った後は、沈黙が永遠に続いた…。
月曜日の夕方、ダウンタウンを歩いていると、また、アウディがクラクションを鳴らした。
「兄貴、デートはどうでした?」
と大声が聞こえたので、
「うるさい!」
と一言叫んだ。
 第39回:チャイナタウン・エレジー・1 ~ルームメイト
第39回:チャイナタウン・エレジー・1 ~ルームメイト