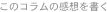第101回:外国で暮らすこと
更新日2009/03/05
私が勤めている田舎町の大学にも留学生が沢山います。
ノーベル賞でも目指して研究をするのでなければ、アメリカを知り、アメリカ人と友達になり、そこそこの英語を身に付けるためには、かえってこんな田舎で学ぶ方が良いのでしょう。
優秀な学生さんは2年もこの大学にいると他の大きな大学や、その専門分野で有名な大学に移って行ってしまいます。彼らにとって素晴らしいことなので、祝ってあげたい気持ちもありますし、私もそのような学生さんには積極的に転校を勧め、他の大学へ推薦状を書いていますが、同時に少し寂しい気持ちが残るのは事実です。
一昨年から、半ば押し付けられるように、国際学生協会(留学生クラブのようなものです)のスポンサー役になってしまいました。他にメキシコ系の学生を中心にしたヒスパニッククラブ、黒人学生のアフロアメリカンクラブ、ポリネシアンクラブなどがあります。
これらのクラブはスポーツや音楽、芸術のクラブと異なり、自分がどこで生まれたか、何人種であるかが大きな要素になります。本来は外国人留学生がアメリカの生活に巧く適応していくように、そしてそれぞれの文化と言えば大げさですが、お国柄をアメリカ人により良く知ってもらうのが狙いです。
私が世話役をしている国際学生クラブの会長さんは、フィリピン人の女学生です。女性の力が強いのか、ネパール、ロシア、日本と代々女性の会長さんが続いています。今メンバーはロシア人、フィリピン人、日本人、ウクライナ人、ペルー人、ブルガリア人、ルーマニア人、ベトナム人 カンボジア人、グアテマラ人、それにアメリカ人です。
そうなのです、面白いことに半数は地元のアメリカの学生なのです。私は国際学生クラブにアメリカ人が入ることに大賛成です。今まで牛と馬だけを相手に育ってきたような全く外国人を知らない地元の牧場育ちの生徒さんが彼らにとって、まるで他の天体から来たような未知の国の生徒さんと仲良くなりルームメイトになったり、恋人同士になるのを見るのは心和む情景です。
日本人に限った事ではありませんが、初めて外国で暮らすときとても大きなストレスが生まれます。旅行しながら、行く先々で土地の人々の心情に触れ、感動しているだけで済ますことができない事態が日常生活のあらゆる面に出てくるからでしょう。
アメリカに着いたばかりの時、留学生に不安はあるのでしょうけど、それを上回る好奇心と情熱を持っています。その興奮期間を第一段階とすれば、第二段階は、少し学生生活に慣れ、学校や町の様子も分ってきたころ、比較文化論時代が始まります。
日本はこうではなかった、なんだこのアメリカのやり方はと、主に自分の国への郷愁から自国が良く見え、アメリカの悪いところばかり目に付き出す時期です。自分が祖国全体を背負っており、この中西部の田舎町がアメリカ全体を象徴しているかのように振舞います。この時期に、日本は、アメリカはと、全体論をよく展開したりします。
第二段階を抜けると自分の国を客観的に外から眺めるようになり、アメリカの(この田舎町のことですが)学生生活を目いっぱい楽しむようになってきます。それが第3ステージです。言葉にもあまり不自由を感じなくなるのでしょう、ジェスチャーも使う若者言葉もまるでアメリカで生まれ育った日系人のようになる留学生も出てきます。
日本人らしくないとさえ見えることもありますが、人は何かを失わずに、新しいものを得ることができない宿命を持っていると考えるしかないのでしょうね。
卒業してから、アメリカで就職し暮らす外国人留学生は80パーセントくらいになるでしょうか、外国人一世としてアメリカでの地位を築いていきます。
そして、アメリカで学んだことを自国に持ち帰ったときが第4ステージです。周りから変に外国ズレ、アメリカナイズされて帰ってきたと見られ、本人も自国にすんなり溶け込むことができない時期です。
彼らが日本なり、自分の国に帰った時に体験する自国の大きな壁は学生としてぶつかったアメリカの壁よりズーッと乗り越えるのが難しいと知ることになるのですが、この二つの壁を乗り越えたときに、本当の国際人が生まれるのでしょうね。
 第102回:シーザーの偉大さ
第102回:シーザーの偉大さ