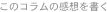第118回:東西公共事業事情
更新日2009/07/16
私でも、こんなに漢字が並んだタイトルをつけることができるのですから、パソコンの威力は絶大です。
山の家から降りて学校までの通勤におよそ1時間ほどかかります。コロラド川に架かっている立派な橋を渡るまで、行きかう車はほとんどなく、快適な山道ドライブなので、1時間のドライブは全く苦になりません。
ところが、昨年の10月に山を降りきったところにある灌漑用水路にかかっているチッポケナ橋の架け替え工事が始まりました。冬の間は灌漑用水を止めるので、それを待っての工事は、時期的にも適切だと思っていました。用水路は幅4、5メートル、両サイドの土手を入れても7、8メートルの幅しかなく、そこに橋があったと気がつかずに渡ってしまうほど小さなものです。
大きなヒューム管を入れて、その上をアスファルトか何かで固め、2、3日で終わるのだろうと思っていたところ、なんと今年の4月半ばまで、6ヵ月もかかったのです。その間、私のような山の住人は、封鎖された橋を横目に5キロも迂回しなければなりませんでした。
私が見ていないときに、工事現場は大いに活気づいているのかもしれませんが、朝晩通りかかる時はいつも、大げさなくらい巨大なパワーショベルやブルドーザー、ダンプカー、クレーンが機械類のお墓のように静かに居座っているだけで、それらの機械が活躍しているのも、人間が忙しく働いているのも見たことがありませんでした。
私が、日本ならこんな工事半日で終わるのにと、盛んにコボシタところ、うちのダンナさん、札幌郊外の手稲駅前のことを思い出させてくれました。
もう数年前のことですが、当時、お姑さんが手稲に住んでいたのですが、春休みをそこで過ごしたことがあります。
ある朝、手稲駅前を盛大に掘り起こしているのに出会いました。沢山の人が忙しそうに働いているのです。駅へ出入りする乗降客のためには立派な通路が設けられ警備員が頭を下げながら、「ご迷惑をおかけしております」と、通勤客を誘導していました。
その日の夕方、札幌から手稲駅に帰ってきたとき、アレッ駅を間違ったか、日付を間違ったかのかなと、自分の頭を叩きたくなりました。駅前は工事の跡形もなくきれいに片付けられ、昨日と全く同じ状態に戻っていたのです。工事の名残りは掘り起こしたところが真新しい黒いアスファルトになっているだけでした。これは日本式の手品だと、感動さえしました。
ところが、一週間もたたないうちに、全く同じところを、また同じようにホジクリ返しているのに出くわしました。誰も見向きもしない工事の内容を書いた立て看板をダンナさんに解読して貰ったところ、前回のは下水関係で、今回のはガス、その逆だったかもしれませんが、というのです。
同じところを掘るならどうして一緒にやらないのだろうという、普通人の疑問はお役所に存在せず、3月の終わり頃に工事は集中しており、毎年こんなことが同じように繰り返されるとはダンナさんの解説です。
お役所が絡んだ工事は可能な限り工期を引き延ばすか、何度も繰り返すかの違いだけで東西どこも同じですね。ただ、予算を使い切ることだけが目的なのですから、効率を最優先させる民間事業のモノサシでは到底測ることができません。
ちなみに、灌漑用水路に架けたチッポケな橋の工事費は一億円相当でした。
 第119回:"純"離れの文学賞
第119回:"純"離れの文学賞