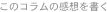第112回:アメリカの裁判員制度
更新日2009/06/04
日本でも裁判員制度がついに始まったようです。
裁判員制度を知るためには、名画を見るのが良いと思います。シドニー・ルメットの名作『12人の怒れる男』です。ヘンリー・フォンダが主演し、陪審員の評決がどのように行われるかが、よく描かれていますので是非ご覧ください。
アメリカでは、イギリスの制度を受け継ぐ形で陪審制度が古くからあります。州や郡によって陪審員の選択の仕方、評決のやり方など異なりますので、一概にこれが現在アメリカで行われている一般的なやり方だとは言えませんが、簡単に説明してみます。
まず、裁判所から手紙が来ます。裁判所と言っても郡の法務官からで、陪臣員の候補になったから何日に出頭せよという通知です。この時点でかなり多くの住民に同じ手紙を送っているので、手紙を受け取ったからといって陪臣員になると決定したわけではありません。
その出頭命令を無視すると、犯罪になりますから、周到できない場合、お医者さんの証明書またはその期間に町を離れなければならない正当な理由などをもっともらしく書いた書面を用意し、提出しなければなりません。平たく言えば、みだりにサボルれないのです。
それから、裁判所に出頭し面接があります。法務官は、信仰やどの政党を支持するかなどについての質問を陪臣員候補にすることは許されません。一般的なことばかりをさりげなく質問し、私が陪審員として偏見のない、公平な判断を下す能力があるかどうかを見るのだそうです。また、秘密厳守とかの義務、裁判の期間中に進行中の裁判に関する情報を得るな(テレビ 新聞、雑誌などを見るな、読むな)とか、ほとんど現実離れした注意事項を読み上げます。
その時になっても、自分がどんな事件の裁判で陪臣員になるのかは、まだ知らされません。人件費の関係でしょうか、事件の重大さによるのでしょうか、陪審員は5人、7人、12人と、そのケースによって異なります。
さて、やっと選ばれ、指定された日に裁判所に行き、初めて他の陪審員、裁判を担当する裁判官、判事、弁護士と対面します。でも、話すのは裁判官だけで、どこかお説教じみた陪審員心得を聞かされます。そして、やっと裁判に立ち会うことになります。
ここの法律では、陪審員は有罪か無罪かだけを判断し、評決します。有罪の場合の刑期は、裁判官が決めます。素人の私がまず驚いたのは、一つの犯行と思っていた事件に実に沢山の罪状が付くことです。一つの犯罪に、たとえば、第二種殺人罪、死体遺棄罪、窃盗罪、不法侵入罪などなどについてそれが当てはまるかどうか、有罪か無罪かを判断しなければなりません。裁判官の教えどおり、その事件に関して判決が下った後でも他言は許されません。
この陪臣員として招集された場合、どんな企業でも、その期間、何時間という時間単位のこともありますが、職場から離れることを許さなければなりません。また同時に、同じ職場に返ることを保障しなければなりません。陪臣員に最低賃金法に基づいた時給が支払われます。裁判所までの交通費などは、自分のポケットから出します。
私のような仕事、教職についている人、大きな会社に勤めている人、公務員は陪審員になっても、仕事上の差し障りは少なくて済みますが、自営業で、自分一人と奥さんだけでやっているお店やレストランのような仕事の人は、店を閉めなければなりません。でも、そんな人たちもグチ一つこぼさず、真剣に陪臣員の役をこなしていました。市民の大切な義務と受け取っているのでしょう。
日本での議論を読むと、人の命にかかわるような重大な判断を貴方は下せるのか、素人に任せてもよいのかという論議が多いようです。西欧人の考え方の基本にあるのは、全くその逆で、そんな大切なことを世間知らず?の裁判官だけに任せられるものか、となるのです。
 第113回:愛とLOVEとの違い
第113回:愛とLOVEとの違い