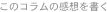第25回:ゲルニカという町の意味(2)
更新日2003/04/17
ゲルニカの町のツーリスト・インフォメーションで、並べてあるパンフレットを手にとっていると、係りの男性が「どちらからですか?」と声を掛けてきた。「いまはマドリードに住んでますが、日本です、長崎」と答えるや「ナガサキ! そうですか。それはようこそ、平和の町へ」と、笑顔で手を差し出す。スペインでは多くのひとがヒロシマ・ナガサキのことを知っていることは以前にも述べたが、ここゲルニカではさらに誰もが「1945年のことでしょう?」とまで言ってくるのには、本当に驚く。町役場の男性がうっかり「だって姉妹都市だから」と誤って思い込んでいたくらいに、とても親しみを感じてくれているのだ。
なぜか。ゲルニカの町のひとびとも、同じような辛い体験をしているからである。
1936年から、スペインでは激しい内戦が行われていた。一方はフランコ将軍率いる国民戦線であり、支持していたのはお金持ちや土地持ちや教会や軍部、それにドイツのヒットラーとイタリアのムッソリーニ。対するは人民戦線で、共和主義者に自由主義者に共産主義者、文化人ほかの外国人による国際義勇兵などが支持していた。
1937年4月26日、この日は月曜で、ゲルニカでは市場が立つ日となっていた。そのため町には近郊からの買い物客などで通常よりだいぶ多い1万人以上のひとがいたし、市の行われていた広場は非常に混雑していたという。
そのとき、空に、爆撃機の一群が現れた。国民戦線に協力するヒットラーにより派遣された、ドイツ空軍コンドル部隊であった。彼らに下された命令は、「殺せる限りの人間を殺せ」というものであったと伝えられている。
近代的に編成されたコンドル部隊は、反撃どころか防御するためのなんらの術も持っていなかったゲルニカの町に、次々と爆弾を落としはじめた。降り注ぐ爆弾を受け、地上では、それはすさまじい光景が繰り広げられた。4時間経ってようやくコンドル部隊が引き上げていったときには、町は完全に破壊され、炎上する瓦礫が一面に広がるばかりとなっていたという。そしてこの空爆で、町の人口の1/3にあたるひとびとが亡くなった。これこそが、ピカソが描いた『ゲルニカ』の姿である。

ゲルニカの町にある、絵を複製したタイル画
この爆撃は、次の2点において世界初だったと言われている。ひとつが、爆弾の種類。爆撃に用いられたのは、開発されたばかりの新型爆弾だった。そしてもうひとつが、編成された空軍部隊による無抵抗の町への無差別な空爆という、近代的な戦争のスタイルだ。たとえば、東京大空襲のような。ゲルニカは、後の第二次大戦で何度も用いられたこのスタイルがどれだけ有効かを確かめるための、実験場とされたのだ。実験! そう、まるでヒロシマ・ナガサキへの原爆投下のように。ひとの死を、数だけで計算するために。むむむむむむむ。
空爆までの経緯や当日の様子、その後ゲルニカが今日まで行ってきている平和の町としての取り組みは、ゲルニカ平和美術館で見ることができる。ドキュメンタリーフィルムや当時を再現した部屋など興味深い展示も多いなか、最上階の壁に記されていたマハトマ・ガンジーの言葉がこころに残った。「平和への道はない。平和がすなわち道である」
Fundacion Museo de la Paz de Gernika
Foru Plaza, 1
94-627-0213
月曜、日曜午後休館
入場料4ユーロ(520円)
それにしても。私はわからなかった。なぜ、ゲルニカだったのだろう?
日本への原爆投下の場合は、「軍事的性格を持つ町で、原爆の威力を性格に判定するためにある程度の広さがあり、それまであまり空襲の被害を受けていない」という基準で選ばれている。戦争中のことなのだから、実験という名目にしろ結局町をひとつ壊滅させてしまうのならば、軍事的性格を持つところが対象となるのが当然のような気がする。
しかしゲルニカの町には、軍事的な要素はこれっぽっちもない。スペイン北部の山に囲まれた小さな町、たとえば人口で比較すると北海道の網走郡女満別のような町を、どうして徹底的に壊滅させなければならなかったのだろうか?
この疑問を解く鍵は、やはりゲルニカにあった。以下、来週に続くのでありました。
ところで、スペインでは2時から4時あるいは5時までが長い昼休みとなる。この時間はツーリスト・インフォメーションも、市役所も、美術館も、閉まってしまうところが多い。なので1時半にようやく町に着いた私は、来て早々にすることがなくなってしまった。そこで、ツーリスト・インフォメーションで教えてもらった地元のタベルナ(居酒屋)へ向かった。
入り口付近のカウンターにたむろして食前の一杯を楽しむ地元のおじちゃんたちの海をかいくぐって、奥のテーブル席へ。本日の定食は6.20ユーロ(約800円)で、前菜に魚介類のスープ、メインにバカラオ(タラ)のパプリカソース煮、デザートにクアハダ(羊の凝乳)を選んだ。これにパンとワイン、エスプレッソコーヒーがついてくる。これだけでも安いと思ったのだが、ワインは1本ドンと出されるし、前菜のスープはバスケットボールが入るような大鉢から好きなだけ取って頂戴だし、バカラオだって私の顔くらいの面積(標準日本人より2割増)がある。しかも、これが、最高に美味い! さすが、美食で名高いバスクである。スペイン版「料理の鉄人」も、ほとんどここの出身なのだな。
カウンターにたむろして食後の一杯を楽しむおじちゃんたちの間を泳ぎつつ、ちょいと参加して軽口を叩きつつ、楽しい気分でタベルナを出る。これから向かう議事堂は、町の高台にある。なだらかに続く坂を、ぽくぽくと登った。3時半、通りに人影はほとんどない。太陽が眩しい。ふと立ち止まって見上げた空が青い。遠くに山の稜線が、霞がかっておぼろげに見える。なんて平和的な光景。だが。
「ここが、4時間も爆撃され続けたんだ」 そう思った瞬間、慄然とした。
 第26回:ゲルニカという町の意味(3)
第26回:ゲルニカという町の意味(3)