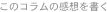第24回:ゲルニカという町の意味(1)
更新日2003/04/10
前回紹介したように、ピカソの大作『ゲルニカ』は、スペイン北部に実在する小さな町の名前である。バスク州ビスカヤ県にあり、人口14.500人、面積8.6km2。本当に、小さな小さな町である。しかし、その名は世界中に広く知られている。1937年4月26日の出来事によって。ピカソが描いた悲劇の町として。そしていまは、平和の町として。

マドリードのソフィア王妃芸術センターでピカソの絵を何度も見ているうち、一度は行きたいと思うようになっていた。ただ、なにしろ遠い。フランス国境まで1時間で着いてしまうような場所にある。しかも小さい町なので、当然のごとく、マドリードからの直行バスはない。だけど今回、思い切って行くことにした。何故と言いねぇ、「平和の町」を訪れるのに、いま以上にふさわしい時期があろうかね?
というわけで4月に入ったばかりのある晴れた朝、というか夜明け前の6時過ぎ、私はそっと家を出た。今回の出発ターミナルは南のメンデス・アルバロ(勝手に通称:浜松町)ではなく、北のアベニーダ・デ・アメリカ(勝手に通称:上野)である。勝手に通称するところの成増あたりの我が家からは、若干近くてうれしい。まぁどうでも良いのだが。
バスのチケットは、事前に電話で買ってある。往復で39.15ユーロ(約5200円)。ただ、そのとき帰りの便も予約しようとしたら「その便はあるかどうかわからないので、当日、現地で確認してください」と断られたのが、ちょっと気になる。4月1日だったのでエイプリル・フールかとも思ったが、スペインの「嘘をついてもいい日」は12月28日だしなぁ。まぁなんとかなるべ、と、バスに乗り込んだ。
7時ちょうどに、バスがターミナルを出た。空はまだ真っ暗だ。それもそのはず、数日前にサマー・タイムへ移行したばかり。つい先週まで、いまは午前6時だったのである。そりゃあ空も暗いぜ。バスはマドリードから一直線に北を目指す。東側の席に座っていたので地平線から顔を出す朝陽を眺めつつ、眺めすぎて眼をやられつつ、まだ夜が明けきらない草原で草を食みはじめる羊を数えつつ、すっかり寝てしまった。
9時過ぎ、ブルゴスという町(勝手にイメージ:仙台)の郊外で20分休憩。カフェ・オ・レとクロワッサンを頼んで、2.40ユーロ(約310円)。街道沿いにつき市場価格より5割増しといったところか。クロワッサンをカフェに浸して食べたいなぁ、でも行儀悪いかなぁ、と可愛くためらってみせたものの、隣で運転手さんがどぼどぼに浸して食べているのを見て、安心してだばだば漬けて食す。朝はこれがいちばん好き。
町を抜けてバスク地方に入ると、風景の美しさに目を見張った。マドリードあたりのパサパサした赤土とは大違いで、ふっくらとつややかな緑色の草が広がっている。羊も薄汚れて「あたしゃ羊に生まれたことを恨みます」なんてかんじじゃなくて白くて丸々と太っていて、それを敏捷そうな牧羊犬が追いかけたりしている。空気に湿り気があるのはスペイン北西部ガリシア地方も同じなのだけど、あちらがポルトガルに似て少し淋しい雰囲気なのに比べ、バスク地方は見事に「豊か!」という雰囲気なのだ。3年分くらいの緑を見たぞと思ったところで、バスは終点のビルバオに着いた。マドリードから395km、東京からだと岐阜県の大垣か三重県の鈴鹿あたりになる。
そこからゲルニカまで33kmを、今度はバスか電車で移動することになる。おっとその前に、帰りの便の予約をしなきゃ。平日で片道10便、週末なら17便が運行されているから大丈夫だろうけど。なぜかみっつのうちひとつしか開いていない窓口に20分ほど並んで、「帰りの便を予約したいんですけど、6時発ので」と言うと、「今日は8時発のしかないわよ」とすげない返事。え? 聞き間違いかと思いながら突っ立っていると、「今日、ストライキなのよ」と説明をしてくれた。
あぁぁぁぁ、やってもうた。スペイン名物ストライキに遭遇。あかん、こりゃやばいぞ。そう言われれば、窓口に「最低限のサービスで営業中」と貼ってある。それでひとつしか開けていなかったのか。仕方なく8時の便を予約し、ツーリスト・インフォメーションの場所を訊く。「あそこの角だけど、閉まってるわよ。ストライキで」 あぁぁぁぁ、やっぱり。ゲルニカに行きたし、行き方はわからじ、ビルバオ初めてで土地勘ないし。
とりあえず売店で市内地図を買う。3.60ユーロ(約470円)。地図を広げたまんま、いろんなひとにゲルニカまでの行き方を訊いてみる。3人から3種類の答えが帰ってきた。ううむ。スペインでは、道を訊いたときに、少なくともふたりが同じ返答をしてくれるまでは、その答えを信じちゃいけない。経験上、そう確信している。最後に、通りがかった警察官がいたので訊いてみると、やっと重複した回答が出た。地下鉄駅へ歩きながら、つくづく思う。日本の交番って、良かったよなぁ。道訊けるし、財布落としたらお金貸してくたし、お腹壊したときはトイレ貸してくれたし、拾った10円持っていったらご褒美に100円くれたし(幼稚園時)。
ビルバオは人口47万人、スペインで7番目に大きな都市だ。もともと造船など重工業で発展してきた工業都市だが、近年はちょっと元気がなくなっていた、らしい。だけどそこから市は、思い切った近代化に出た。1995年に開通した地下鉄は、香港の空港も手がけた世界的に有名な(と書いてあった)ノーマン・フォスター卿のデザイン。さらに1997年には、ニューヨーク、ヴェニス、ベルリンで高い評価を得ていた(と書いてあった)グッゲンハイム美術館を誘致してオープン。費用は130億円とか。小樽の裕次郎記念館のようなものかもしれない。違うか。
てなわけで、ノーマンでフォスターな垢抜けたデザインの地下鉄に乗り、教えられたところで降りて、ゲルニカ行きのバスを待つ。もちろん、ここでも何人かに確認して「重複回答確保の原則」を徹底。やがて、ゲルニカを通る近郊バスがやってきた。運転手さんに「そこに座っとくから、ゲルニカに着いたら教えてね!」と頼んでから、いちばん前の座席に座る。ゲルニカまでは約45分、片道2ユーロ(約260円)。
濃い緑色をした山をいくつか越え、小さな盆地に出たと思ったら、そこがゲルニカだという。礼を言って、バスを降りる。行き交うひとに再び何度も道を訊きながらツーリスト・インフォメーションに着いたときには、もう1時半になっていた。ゲルニカはやはり、遠かったのであった。
 第25回:ゲルニカという町の意味(2)
第25回:ゲルニカという町の意味(2)