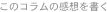第58回:Cambodia (3)
更新日2007/05/24
カック湖の湖畔には規模は小さいながらも、バックパッカーを相手にしたちょっとした安宿街が成立しており、安宿の他にも西欧風の料理を出す店や各格安旅券の発行所もあった。そんな格安旅券を手配する店のひとつで、ジャングルの中を流れるトレンサップ川を遡って、カンボジアで一番大きなトレンサップ湖まで行くスピードボートのチケットを買った。
ポルポト亡き後のカンボジアはかなり治安も安定してきていたが、まだジャングルの奥地にはゲリラや、金銭目的の山賊まがいの輩が存在し、そんな中を走るスピードボートに乗るのはあまり気持ちのよいものではなかったが、それでも陸路を行くよりは幾分安全ということであった。
トレンサップ川で待ち受けていたスピードボートは想像していたものよりは遥かに立派な20人乗りほどのモーターボートで、しっかりとしたエンジン音で進む航行スピードもなかなかのものであった。こういうボートに乗ると後で後悔することになるのがわかっているのに、蒸し暑い船室内に篭っているよりは、日差しは強いながらも川を進む船を切る風のおかげで涼しい船の屋根の上に繰り出して、みんな茹蛸のように真っ赤に日焼けすることになるのがアジアの流儀である。
水上生活者の暮らす小船型の家があちらこちらに浮かぶトレンサップ川を3時間ほど遡り続けて、スピードボートは広大なトレンサップ湖へ入った。乾季だというのに、それでも茶色い水をなみなみと湛えた東南アジア最大の湖には、我々のスピードボート以外にはほとんど行き交う船もいないという、いかにもジャングルの奥地らしい風景だった。この湖は、世界最大の淡水魚漁獲量を誇り、カンボジア国内の淡白質摂取源の6割を供給しているという。
湖の上をさらに2時間ほども進んだ頃だろうか、遠くに湖上で待ち受ける小さな3隻の木製簡易ボートが見えてきた。我々を乗せたスピードボートは、その3隻の簡易ボートへするすると擦り寄っていくと、湖の真ん中で突然止まった。
今までのんびりとした雰囲気の漂っていた船上にピシリとした緊張が走る。乗客の10数名は全員外国人だったのだが、盗賊が出ることもあるというこの湖の真ん中で、突然ボートが止まったことに誰もが不安を隠せなかった。しかもよく眺めてみると、周りに停泊している簡易ボートに乗っている男の一人は自動小銃まで持っているではないか。
もちろん乗客の外国人の中にカンボジア語を理解できる者はいなかったし、船員にも英語を理解できる者はいなかった。それでもかまわず乗客の中の一人が、英語で船員に、「いったいこれは何なのだ」と問いかけるのだが、船員はそんな質問などいっこうに介することなく、忙しそうに船の中にあるバックパックをせっせと小船に載せ移しだした。
何が起こっているのかまったく状況を把握できないままに、我々はただ呆然とそれを眺めるしかなかった。船員がまったく説明もせずに荷物を簡易ボートに移し出したために、これはもしかしてゲリラか盗賊ではないのかなどと私も考えていたのだが、またもや先の乗客が、「バックパックを移すのはやめろ」というようなことを手振りを交えて船員に伝えた。
もちろん自動小銃を持つ男がいる中で、まったくの無防備な我々には彼らの指示に従うしか手はなかったのだが、その苛立ちを堪えた乗客の問いかけについに答える必要があると感じたのか、船員は手振りで、「何を勘違いしているのだ。だいじょうぶ、だいじょうぶ」というようなことを笑顔とともに伝えてきた。その笑顔と対応振りがあまりに緊張感のないものだったので、とりあえず別段危険な状況ではないのだろうという思いが乗客の間に静かに広がった。
簡易ボートへそれぞれ5人ずつほどに分けられて荷物と一緒に乗せられ、そこから1時間ほど湖を進んだ。するとどうだ、今度はまるで丸太を切り抜いただけのような原始的な手漕ぎのボートが湖上に待ち受けており、それにまた乗り換えさせられることになった。
「おいおい、またかよ。しかも今度はいつ沈没してもおかしくないような小船じゃないか」と不安になったが、そうは思っても何もない湖の真ん中では彼らに指示されるままに乗り換えるしかなかった。

その小船に乗り換えてさらに20分ほど進むと、泥でぬかるんだ湖岸に貧しい漁民たちが暮らす小さな集落に到着した。その漁村の貧しさは、これまでに通過してきた中国やベトナムのどんな村よりも貧しいもので、子供たちには明らかに栄養失調気味である身体的な特徴が現れていた。
泥の湖底に船底を擦りながらビーチに船が乗りつけると、子供たちが慣れた足つきでぬかるんだビーチを歩いて船に寄って来て、小さな子供は荷物を、そして大きな子供は乗客をおんぶして岸まで運んでくれた。もちろん、この運び役が彼らの貴重な現金収入の機会であるのは言うまでもないが、陸に上がってからも大量の子供たちに囲まれて、それをくれ、あれをくれとせがまれるのを断りながら進むのにはかなりの労力を要した。こういう場面では何かあげたくなってしまうのが常であるが、いったんこの客は何かをくれるということが周りの子供たちに知れ渡ると、それこそ収集のつかない事態を招くことになる。
プノンペンからこの漁村まではなんとかやって来ることができたが、ここからアンコールワットがあるシェムリップの町まではいったいどうやって行けばよいのかということは、まったくわからなかったが、そんな心配をするまでもなく、湖岸にはシェムリップのゲストハウスと提携している、バイクタクシーのドライバーたちがプラカードを持って待ち受けていた。
とにかく公共の交通機関などあるわけもなく、こんな場所にぽつんと取り残されてしまったりしたらそれこそ問題である。そういうわけで、こういう場面では必ず値段交渉をする姿を見ることができるはずの貧乏旅行者たちも、バイクタクシーが足りなくなってしまう前に、あっさりと最初に声をかけてきたドライバーについて消えていった。
バイクタクシーであるから、ドライバーと大きなバックパックの他には、一人ずつしか乗客は乗れないのだが、エリカの乗ったバイクは自分の乗ったバイクよりもずいぶんとエンジンが元気で、一緒に出発したのにもかかわらずあっという間に視界から消えてしまった。
サービス精神という概念がないからなのか、英語がまったく通じないからなのか、エリカのバイクに追いつけといっても、まったく我関せずでのんびりと進む自分のバイクと、エリカはエリカで私のバイクが追いつくまでスピードを落とせと言っても、まったくスピードを緩めようとしないドライバーに閉口したらしい。これが盗賊団だったら、それこそこの場所で旅人をさらって行ってしまえば、簡単に拉致が可能な場面なのだが、それでも選択の余地がないのだから、こちらとしてはそれを承知でこのバイクを利用するしかなかった。
乾季の時期だけに現れる道路らしい道路もない悪路を、バンピンと飛び跳ねながら進むバイクにも心地がよいものではなかったが、さらにその心地悪さを増幅させたのは、ときおり草むらの中に出現する髑髏マークの看板であった。そう、この地帯は盗賊が未だに存在するだけではなく、地雷原でもあったのである。
。
-…つづく
 第59回:Cambodia
(4)
第59回:Cambodia
(4)