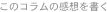第52回:Vietnam (7)
更新日2007/04/05
もちろん一緒に歩くとはいってもそれほど大きな町ではなかったので、しばらく歩いているうちに民家の立ち並ぶ集落を越えて、のどかな水田が広がる地域に出た。そこで出会った光景は、まるで戦中戦後の日本の写真集を見ているような、不思議な懐かしさを呼び起こすものであった。
「この光景を見ることができただけでも、この少年たちに感謝しなければいけないな」、などと思いながら来た道を一緒に引き返し、町の出口付近まで来た時のことだった。二人の少年たちが、「のどが渇いた」と言う。その切り出し方の不自然さにちょっとひっかかるものを感じながらも、まだ暑さの完全に収まりきっていない道を案内してくれたのだから、とにかくお礼に何かをという気持ちで、何軒か並ぶ店の一軒でジュースを買ってあげることにした。
ところがこの少年たち、「楽しかったのでもう少し話が一緒にしたいから、すぐそこの簡単な座席がある売店で一緒にジュースを飲みたい」と言い出した。
この時点で耳の裏をぬめっと撫でるような嫌な感じがしたのだが、ここまでずっと親切に案内してくれた少年たちの申し出を断るのも悪い気がして、ついついその誘いに乗ってしまった。席に着くと、すぐに彼らは大好物だというレッドブルを4本注文した。
ベトナムでは、国境入りしてすぐの時点でフレンドリーなバンの少年に一度痛い目に合わされているので、子供とはいっても油断してはいけないという気持ちが、まさかとは思いながらも今頃になって沸いてきた。そこで、まずは自分たちが飲む前に、このレッドブルの料金を先払いしたいと店の主人に告げることにした。
するとどうだ、店の主人はお前が何を話しているの分からないといった表情しながら、まあ飲め飲めという仕草で店の奥からレッドブルを出してくる。これはちょっと不味いことになったぞと思いながら、少年たちの方を見ると、彼らは慌ててレッドブルの缶を店主から奪い取るように受け取ると、そのままトンズラしてしまったのだ。さて、こうなると問題である。
観光客が多くいる町の中心部からそれほど離れているとはいえないとはいえ、どう考えてもここは自分たちにとって助け舟が通りかかることはないであろう裏町。それに少年を追おうにも、レッドブルを受け取るが早いか、あっという間にどこかへ消え去ってしまっていた。
とにかく、彼らのレッドブル代は払わないことには、こういう輩は満足しないのは間違いない。そこで、「その料金だけは払うから、いくらか言ってくれ」と店主に英語で伝えた。するとどうだ、先ほどまでは英語なんぞ分からないという素振りをしていたのに、「2本だから20ドルだ」と上手くはないにせよ、きちんとこちらにも伝わる英語で答えてきた。
これだから参ってしまう。さすがに20ドルは、「はい、そうですか」と言って渡せる金額ではない。何しろ今夜の宿ですら、1泊5ドルの町なのだから。
そこで駄目は承知で、「いや、1本10ドルはないだろう」と伝えると、今度は、「それは輸入品だから高いのだ」と言ってきた。確かに高いのかもしれないが、町中では1本6,000ドンそこそこの値段で売っているのを我々も確かに見ていた。だがそんなことを言っても通じる相手でないのはもちろんである。
なんだかまた揉めるのも疲れるので、「じゃあ、2本で3万ドン払おう」と自分にしてはかなり甘い条件を出したのだが、店主は頑として譲らない。馬鹿らしくなって、テーブルの上に3万ドンを置いて立ち去ろうとすると、店主はガシッと乱暴に私の胸倉を掴んできた。
そうするつもりはなかったのだが、あまりの乱暴な仕草に思わず反射的に胸倉を掴んだ彼の腕を逆に捻りあげてしまった。と同時に、「やめろっ!」と大声で叫んだのだが、その声に反応して、これまで遠巻きに眺めていた周りの住民たちが、ぞろぞろとこの店に集まってきた。
しかもこの住民たち、払わないとここから出られないぞという剣幕で、「払え、払え」と叫んでくる。またである。もとはといえばこんな知らない土地で、いくら少年とはいえ信用してしまった自分が悪いのだが、それにしてもこれで2度目だ。中国では散々嫌な思いをしたが、とりあえずこういった地元民総出の脅しの類は経験しなかった。
まだ日が暮れるには早かったかもしれないが、この状況はあまり心地のよいものではなかった。ただし、今回はバックパックという大きな荷物を背負っていない身軽さや、胸倉を掴まれたことで自分の中の怒りが大きく膨らみすぎていたこともあって、かかって来るのなら暴れるだけ暴れてやるぞというような気持ちになっていたことは確かだ。
プラスチックのテーブルに向かって、できるだけ大きな音を立てるように平手でバッーンと、先ほどから用意してあった3万ドンを叩きつけ、再びその場を去って歩き出した。
その音に驚いたのか、周りの住民たちは誰も手を出してこなかったが、店主はそれでもまだ脅しをかけるような威嚇の眼差しでさらに行く手を塞いでくきた。苦々しい顔をした店主の後についてきた奥さんの胸元をふと見ると、そこには小さな赤ん坊がいた。そしてその子がこちらを見てウギャーウギャーと泣くのだ。
とにかく、何かとてつもなく嫌な膿のような感情が自分に対して巻き起こってきた。騙す方が悪いに決まっているのだが、こうやってお金を持っている側が、そこまで横柄な態度で跳ね返すというのも、それはそれでどうかしているのだ。しかもその原因となる不用心な状況は、自分が作ったといえなくもない。
また負けた。今度はエリカの方が先に「払いましょう」と声に出した。何に負けたのか分からないが、とにかく何だか負けてしまったような気持ちになりながら、彼にこれでもういいだろうと、さらに3万ドンを手渡した。さすがに彼ももう我々を追っては来なかった。
昼間のウキウキした気持ちはどこへやら、二人ともすっかり疲れきって重たい足どりで、ホイアンの町へ戻り、観光客の集まる賑やかなチャンフー通りを避けて、気持ちを落ち着けるためにトゥボン川の辺へ向かった。日が暮れた後の川辺には、ホイアン名物のランタンの明かりが川面に揺れ、顔を撫でていく風も興奮した気持ちを落ち着けてくれるような涼気を含んだものだった。
そんな、少しずつ落ち着きを取り戻してきた我々の側へ、手にいくつかのお土産を手に持った女の子が寄ってきて、何か買ってくれないかと尋ねる。とりあえず、今はお土産を買うという気分にはとてもなれず、できればそっとしておいて欲しかったのだが、それはあくまでもこっちの勝手な都合であって、余所者としてここへ来ているお金持ちの外国人から、少しでも多くの現金を稼ぐのがこの小さな女の子と家族の生きる糧なのだろう。
「今はお土産はいらないから、ごめんね」と、エリカが伝えると、女の子が返してきた言葉は、「ファック・ユー」であった。その意味を彼女が知っているのかどうかは疑問だったが、お金を使わない旅人は、彼女にとってはファック・ユーなのかもしれなかった。
-…つづく
 第53回:Vietnam
(8)
第53回:Vietnam
(8)