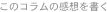第56回:Cambodia (1)
更新日2007/05/10
シンカフェが運営する格安バスを使い、サイゴンを発ってカンボジアのプノンペンへ向かった。片道5ドルの格安バスだから、もちろん本格的なバスというよりは大きなバンといった方が相応しい車だったが、とにもかくにも国境を越えて半日がかりで移動するバスの料金がたったの5ドルというのは、やはり貧乏旅行者にとってありがたいことには違いなかった。
イギリス人の若者が昼メロのような目つきでベトナムの女の子と熱いキスを交わし、検問所を出たとたんに大きな声で、「さあ、カンボジアではどんな女の子が待っているかな」なんて仲間とやりあっているのを見て、こんな馬鹿げたメロドラマも、ここでは毎日のように繰り広げられているんだろうななんて思いながら、ベトナム国境とカンボジア国境の間にある300mほどの緩衝地帯を歩いた。
経済発展の著しいサイゴンを離れてカンボジア国境へ向かうにつれて、車窓から覗く風景も少しずつのどかなものへと変化してきたが、これまで旅を続けてきて、あれほど物価の安い国だと感じていたベトナムが、いやいや実は大した経済大国じゃないかと錯覚させられるほどに、緩衝地帯の先にある掘っ立て小屋のようなカンボジアの国境検問所の姿はみすぼらしかった。

ここで紙切れに入国の日時と氏名を記入して、検問らしい検問もないままにカンボジア入りをすると、先ほどまでのアスファルトで舗装された通りに、コンクリートのビルディングが建ち並ぶベトナム側の光景とは似ても似つかない、剥き出しの赤茶けた大地に、遮るもののない空がどこまでも広がっていた。
空っぽの大地に待つシンカフェの手配するプノンペン行きおんぼろバスに乗り込むまではなんの苦労もなかったが、未舗装の大地を走り出したとたんにボッコンボッコンと跳ねまわり、激しい振動が続くドライブの間中、スカスカになったクッションのシートに尻を叩きつけられる時間が続いた。
バスが走り始めて1時間も経ったころだろうか、突然に空がどんよりと黒ずんできたかと思うと、つい先ほどまで果てしないほどに広がっていた空から激しいスコールの雨が降り注ぎはじめた。こうなるとクッションがないのがただでさえ辛いと思っていたバスの旅に、さらに苦行が重なることになった。
もうもうと砂煙を上げていた乾いた赤土の道路はみるみるうちにぬかるんだ泥道へと変化し、縦揺れの激しかったバスの動きに、泥にタイヤをとられてニュルリと不安定な横揺すりが加わった。そのせいで先ほどまでは何とかこのドライブに耐えていた乗客も、ついに地獄の拷問の最中のような青白い顔色に変わっていくのが見てとれたが、このおんぼろバスはそんな車酔いに弱い乗客だけではなく、ほかの客にも平等に苦しみを与えようというのか、屋根がついているのが信じられないほどにあちらこちらからボトボトと雨が振り込んできて、バスの中の乗客と荷物をあっという間に水浸しに変えていった。
突然のスコールもなんとかやり過ごし、ぬかるんだ赤土の泥道をさらに1時間ほど走ったところで、大きな川に出合ってバスは止まった。確かに大きな川ではあるが、向こう岸が見えないというほどの大河というわけではない。それでもこのカンボジアという国の経済力からすると、この大きな川に橋をかけるほどの資金的な余力はないのであろう、サイゴンとプノンペンを繋ぐという、ある意味ではこの国の幹線道路であるはずのこの道路ですら、いったんここで道は途切れて、バスもこの川の両岸を繋ぐ渡し舟に乗らなければ向こう岸へは渡れないという具合であった。
渡し舟がこちら側の岸に着くまでの間、バスは乗客を乗せたままじっと港で待っているのだが、これを最大の商売機会としている子供たちが、手に手にコーラや小さなお土産などを持ってバスの窓へ押し寄せてくる。その子供たちが身にまとっている服装や、土埃にまみれた顔つきは、改めてこの国の貧しさを再認識させてくれた。

半日をかけたバス旅の後でやっと到着したプノンペンの街並みは、すでに夕暮れであったということもあって、昨日まで過ごしたサイゴンの賑やかさとは打って変わったように、少しばかり危険な香りもするアメリカのスラムに近い雰囲気を漂わせていた。
薄暗くなったこの寂れた街の中で、右も左も分からないままに重いバックパックを背負って宿を探し彷徨う気はもちろんおきなかったし、何よりもおんぼろバスの長旅で疲れきっていた我々は、バスの運転手が乗りつけた安宿で素直に夜を過ごすことに決めた。
しかしこの安宿、廊下の電球すら切れていて、真っ暗で不気味な階段を4階まで昇り降りしなければならないし、電源を入れれば今にも振り落ちてきて首切り刃と化しそうな大きなファンが備え付けられた窓のない部屋には、静かに横になってもギシギシと煩い錆付いたベッドに、いつから日に干していないのかわからないほどジットリとした汗臭いシーツが敷かれてあった。
とりあえず疲れてはいても腹は減るので、宿の横にあった小さな店でマンゴーをいくつか買ってそれを部屋で食べたのだが、こんな日はうんざりするような出来事が重なるもので、口の中に何かニチャニチャする感覚を感じてマンゴーを改めて凝視してみると、ただでさえカビ臭い気持ちの悪い部屋の薄暗い電灯の灯りの下に浮かび上がったのは、マンゴーの甘く柔らかい肉の中に蠢く、小さくて白い蛆のような無数の虫であった。
-…つづく
 第57回:Cambodia
(2)
第57回:Cambodia
(2)