第26回:バルセローナの南京虫 その2

現在のバリオ・チノ界隈の光景
バリオ・チノ(Barrio chino;中国人街)は1930年代にジャン・ジュネが徘徊した時とあまり変わっていないように思われた。狭く日当たりの悪い小路にすえたような臭が漂い、3、4階建てのピソが肩肘を寄せ合い、通りに面した窓からは狭い路地に張られた洗濯物を干すための紐が張り巡らされ、その紐に臆面もなく垂れ下がっている超弩級のパンティー、ブラジャー、下着、そしてその下の路地に立つ大年増の街娼、どぎつい化粧をした男娼たちが、ジュネが描いた当時のまま、化石のように立っていた。
それらのピソの1階に当たる小路に面した地上階に数々のバール(Bar)がある。間口が2、3メートルしかない八百屋、魚屋、雑貨屋、石炭屋(暖房や湯沸しのための)、乾物屋、鶏肉屋、牛豚肉屋、馬肉屋などが軒を連ねていた。
暗いピソへの入口には30cm四方くらいのブリキの看板が張ってあり、そこに“P”とか“H”、“F”、“HS”の文字が浮き出ている。それが木賃宿のマークで、Pはペンション、HSはホステル、Fはフォンダ(飯付き木賃宿)、Hはホテルを意味する。そしてHのホテルには星が一つから5つまで付いていてるが、バリオ・チノにはHのホテルは当時存在しなかったと思う。
バリオ・チノでは、これらの宿は長期滞在者の下宿になっていた。流れの数泊するだけの客は歓迎されない。私が数軒断られた末、泊まったペンションは、パラレーロ通りから20~30メートル薄暗い脇道に入ったところにあった。
狭い階段を登り、辿り着いた部屋は寝心地の悪そうなベッドが片隅にあるだけの、こんな狭い部屋が西欧にも存在するのかと呆れたほどだった。だが、横浜の場末で間借りしていた『聚楽荘』やマキシモの屋根裏部屋で鍛えられていた私に異存があるはずもない。唯一の救いは、細長い小さな窓があることだった。
私はショルダーバックをベッドに投げ出し、バリオ・チノの探索に乗り出したのだった。
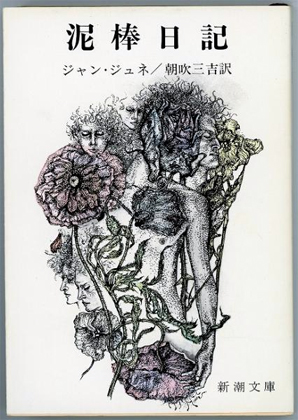
ジャン・ジュネ著『泥棒日記』
ジャン・ジュネがフランスの官憲から逃れるようにスペインに流れ、バリオ・チノを彷徨ったのは1932年、彼が二十歳の時のことだった。それから、何度もの出たり入ったりを繰り返していたが、20代前半をここで過ごしている。
「当時、スペインはいたるところに寄生虫、つまり、乞食の群れがうようよしていた。乞食たちは村から村へと移り歩き、暖かかったのでアンダルシアへ、富んでいたのでカタルーニャへと行くのだが、その他どこでも国中が我々には暮らしよかった」と彼は言っているのだが、それは70年代になってもそんな事情は変わらなかった。スペインは我々貧乏バックパッカーにとっても棲みやすく、汽車、バスなど公共の運賃も食べ物も安く、旅行しやすいところだった。おまけに、スペイン人の開けっ広げな性格も、我々に長居をさせる要因だった。
一体、私自身、何を求めてジャン・ジュネが20代の前半を過ごしたバリオ・チノをうろついたのか分からない。彼の言う“汚エツにまみれた豪奢”を垣間見ようとしただけだったのだろう。ジャン・ジュネは、「私は二十歳だった。もし二十歳という年齢が一滴の涙の明澄さを持っているとすれば、どうして私は、鼻の先に落ちそうになっている滴をも、それに対すると同じ感激をもって飲まないわけがあろう。私はその頃はすでにそれが平気でできるくらいに汚わい復権の道を進んでいたのだ」と書いている。
二十歳にしてジャン・ジュネは、それ以上落ちようもないほどのどん底にあり、同時に透明な目を持っていたのだ。自分にはジャン・ジュネの絶望のカケラもなかったし、彼の生き方を自分に当てはめることなどハナから不可能、なしえないことだとは十分以上に心得ていたつもりだ。ただ、青春時代に感銘を受けた文学者の足跡をミーハーよろしく辿りたかっただけなのだろう。小説にアテラレ、文学碑巡りをしているオネーチャンと同類だと言われてもしょうがないと思う。若い時の感激、感銘の半ばは思い込みによるものだ。
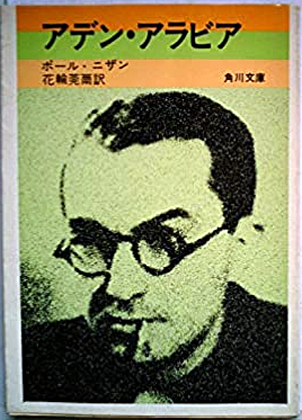
ポール・ニザン著『アデン・アラビア』
私の思い込みが激しかったもう一冊の本は、ポール・ニザンの『アデン・アラビア』だった。「僕は二十歳だった。それが人生で最も素晴らしい年齢だなどと、僕は誰にも言わせはしない」と始まる本は衝撃的だった。そして、「若者にとって何もかもが破滅の危険となる…」と続くのだ。
ポール・ニザンとバリオ・チノは無関係なのだが、わずかながら繋がりがあるとすれば、ポール・ニザンはアンリ4世高等中学校でサルトルと同期で、校長と議論し、もめ、共に学校を辞めている。そして、ルイ大王高等中学校、エコール・ノルマル・シュペリール(高等師範学校)とエリート中のエリート、フランスを代表する知的エリートの道を歩むことになる。サルトルはジャン・ジュネの並外れた才能を逸早く見い出し、出版の世話をし、後にジャン・ジュネが終身刑(10回目の有罪判決)に服すところを、ジャン・コクトーらと救命運動を展開し、大統領の恩赦を引き出している。そして、『聖ジュネ』という大書を書いている。
そして、私が二十歳の時は、学生紛争華やかなりし時で、どちらかといえばノンポリに分類されるであろう私は、運送会社のメッセンジャー・ボーイのアルバイトをしながら、古本を漁り、月に何枚かのレコードを買い、横浜の場末のアパート『聚楽荘』の部屋で、レコードをかけながら本を読むのが楽しみという生活をしていただけだ。
ここバリオ・チノで、若きジャン・ジュネは、スペイン人、サルバドールと関係を持ち、その後、ユーゴスラビア人の片手棒、スティリターノに仕える日々が続くのだ。ジュネはサルバドールやスティリターノが引っ掛けてくる、船員たち相手に男娼として淫売するのだった。
彼らが溜まり場にしていたダンスホール『クリオール』は遠の昔に消えていた。
昼食は『カサ・ホセ』(ホセの家)で摂った。カサ・ホセは角地にあり、その2面を高いガラス戸で囲ってあるだけのレストランで、一見、雑貨屋なのか酒屋なのか、何をやっているところか掴みどころがないレストランだった。貧乏旅行者の間ではチョッとした有名な店だったが、客の90何%かは地元の労働者、バリオ・チノ界隈で小さな商いをしている人たち、娼婦、オカマの男娼たちで、流れの旅行者は極少数のよそ者だった。
これが、営業を始める前には空席(すべて相席だった)がビッシリと埋まり、テーブルにデンとばかり置いてある“サヴィン”(SAVIN)という安ワインを勝手にグラスに注ぎ飲んでいるのだ。下戸の私の意向など無視し、薄汚れたデュラレックス(Duralex)の落としても割れない丈夫一点張りのグラスに、合席の男がいかにも自分のモノのようにワインを注ぎ、勧めるのだった。テーブルに置いてあるワインは、グラスで一杯だけ飲もうが一瓶空けようが同じ料金だった。
常連ばかりだから、中はわめき立てるような会話、騒音で満ち満ちている。出入り口のガラス戸周辺には、今にも倒れてきそうなほど高々とワインやミネラルウォーターのケースが積み上げられている。十数脚のテーブルもぎっしり詰め込まれているから、ウエイターをやっている店主のホセ自身も回りきれず、この皿を向こう端に回してくれとやるのだった。
もちろん、複雑なメニューなど存在せず、3、4皿の前菜、4、5皿のメインから選ぶ方式だ。拘置所のぬるい食事を旨いと感じる舌の私が言うのだが、少々の清潔感と騒音を譲歩すれば大満足の料理だった。
実際、私は良く歩いた。私の旅行の遣り方は、モッパラ脚に頼っていた。暇さえあればホッツキ歩いた。バリオ・チノを文字通り隅から隅まで、ジャン・ジュネの幻を追うように徘徊した。バールでトルティージャ(イモと玉ねぎ入りのオムレツ)にバーラ(棒パン、バゲット)のカケラ、カーニャ(グラス売りのビール)をウソみたいな値段で摂り、いざ私のペンションに戻ろうかという段になって、ショルダーバッグを置いてきたペンションの所在が分からないことに気が付いた。
確かにパラレーロ通りにあったはずだが、カルメン通りだったかも知れず、不安になり出した時、見覚えのある真っ暗な穴倉のような入口に“P”のマークを見つけたのだった。小さなガラス戸の奥にいる親父を呼び出し、重い鉄の鍵を受け取り、光源から遠く、真っ暗闇が溜まっている磨り減った木の階段を上り、ベトつく手すりで身を支え、ようよう部屋に辿り着いたのだった。
※注:『泥棒日記』は新潮文庫の朝吹三吉訳、『アデン・アラビア』は花輪莞爾訳による
 第27回:バルセローナの南京虫 その3 第27回:バルセローナの南京虫 その3
|



