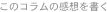第128回:日本人と文化の厚み
更新日2009/09/24
日本に行くたびに感心するのは、女性、主に専業主婦の方々のエネルギーです。人を押しのけるオバタリアンのバイタリティーのことを言っているのではありません。すべてとは言いませんが、大半の主婦が何かにひたむきに打ち込んでいるように見えるのです。それは暇つぶしや趣味の域を超え、本当の芸術に迫っているようにさえ見えます。
昔、私にお琴を教えてくださった先生は、銀行員でした。銀行の同僚の人たちも、彼女がお琴の大先生だとは知らなかったことでしょう。彼女は銀行で働く傍ら、趣味でお琴を弾くというような中途半端な態度ではなく、お琴に全身全霊をかけていました。
私の義理のお姉さんたちも、すでに皆老齢ですが、一人は50年以上もコーラスに打ち込んでいますし、もう一人は社交ダンスを、もう一人は絵画を生涯続けています。そして、それぞれ賞を貰ったり、優勝したりで評価を受けています。
うちのダンナさんの友達にも、忙しい会計事務所を経営しながら、30年くらい俳句を作り続けている人がいます。彼の俳句は、毎月その種の雑誌に載っています。彼の奥さんは、カッポレの名取になり、お祭りだけでなく、老人ホームなどの慰問に出かけ、踊りを披露していますし、別の友人の奥さんはフラメンコダンスを三十数年踊り続けています。
一般的に日本の主婦は、子供ができて、子育ての期間中、外に働きに出ないので、一旦子供たちに手がかからなくなったら、充分自由に使える時間があるのは事実でしょう。それに比べ、アメリカでは専業主婦はむしろ珍しく、育児をしながら定年まで働きます。しかし、日本とアメリカの主婦が仕事以外の習い事、芸術に没頭する度合いの違いは、持てる時間の差だ、と言って割り切ってしまうことができないものがあります。
芸術への渇望、一つのモノゴトに対してのひたむきな打ち込み方、そして一度始めたら何十年も続ける粘液質の継続性が、日本人にはあるように思えるのです。
アメリカの私の周りに、日本人のレベルではないにしろ、豊かな趣味人と呼べるような人は見当たりません。私の妹たち、義理の妹、叔父、叔母、従姉妹、友達に、彼、彼女はあのことに関してはディレッタント(dilettante;芸術愛好家、好事家)だと言える人が全くいないのです。これはショッキングな事実です。
強いて言えば、私の弟はトロンボーンを長年吹き、地方のジャズバンドやオーケストラで演奏していますし、義理の弟は日本の建築と禅に凝っているくらいでしょうか。二人ともハイテック会社の重要な地位にあり、とても忙しい人生を送っていることが共通しています。
この二人より、もっと暇があるはずのアメリカ人たちは一体何をしているのでしょう。皆が皆、テレビの前でポテトチップを食べているとは思いたくありませんが…。
日本のように厚みのある文化背景があってこそ、そこから一人の偉大な芸術家が生まれるのでしょう。
私は大学を出て、すぐに日本に行きました。そこで、英語を教えながら、日本語とお琴を習いましたが、日本にいた10ヵ月の間に、モノを学ぶ態度というのでしょうか、勉強するというのはどういうことだと日本人から教わったような気がします。
何事においても集中し、継続し、努力するのが基本で、そうしなければ、決して対象とした目的に近づけず、その周囲をブラブラ回っているだけであること、本当の喜びは、全霊を打ち込んだ時に初めて訪れるものだと知ったのです。
まだ、外国人が珍しい時代だったので、一日に2、3時間英語を教えるだけで安楽な生活ができました。ぬるま湯に浸かったような、偶然英語圏に生まれ育ったというだけで、英語を教える化石のような不良外人が回りに沢山いました。私もその仲間に入りそうだったのです。
そんな生活を打ち切り、もう一度勉強し直すことにしたのは、学問、芸術に対する日本人の真摯な態度に影響を受けたからだと思います。
この原稿を読んだ私のダンナさん、「少し日本人を買いかぶりすぎじゃないか、日本にもどうしようもないグータラは沢山いるさ」と言いますが、文化の絶対的な厚みは比べようもないと信じています。
 第129回:情操教育と学力の差
第129回:情操教育と学力の差